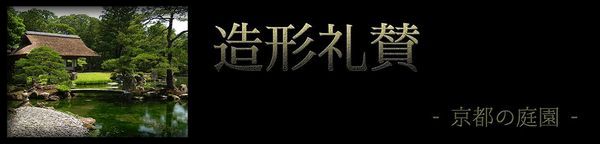紫宸殿南庭
明治の東京遷都まで、伝統と文化の中心としての機能を果たした京都御所。
現在の御所は、平安京がつくられた当初の場所とは異なり、室町時代から形を変えながら今の形が整ったとされています。
政権の中心がが板東に移った鎌倉時代、天皇家の困窮が目立った室町時代、
実質的な権力を失いながらも権威的な存在として存続した安土・桃山、江戸時代と、
政治的な中心はつねに武家に握られてきましたが、
日本文化の源流となる「繊細な美しさを讃える文化」は京都御所が発信地であり続けました。
建造物のほとんどは江戸末期の再建で、おそらく庭園も時代とともに形を変えているとは思いますが、
王朝的な雰囲気はそのまま。
禅宗寺院などの庭にも影響を与えた、一面に白砂が拡がる紫宸殿南庭、
雅やかさを演出する丸みを帯びた植栽が特徴的な御池庭、商家や料亭の洗練された坪庭に通じる御内庭など、
庭園文化の面でも京都御所が他に与えた影響はとても大きいのではないでしょうか。

庭園(御池庭)

庭園(御内庭・坪庭)

 清涼殿
清涼殿 小御所・御学問所・御常御殿
小御所・御学問所・御常御殿 御所の風景(建礼門、障壁画など)
御所の風景(建礼門、障壁画など)
京都御所や仙洞御所を含む区画は正しくは「京都御苑」ですが、
地元では区別が曖昧で、京都御苑のことを単に「御所」と呼んでいました。
だいたい「御所」(=御苑)は散歩や子どもの遊び場として行くくらいで、
近くに住んでいる人は本来の京都御所には特に関心がないというか、あまり念頭になかった気がします。
タクシーでも「御所」と言えば、京都御苑のことと理解してくれるはずですが、
御苑は広いので、例えば京都御所拝観の場合は「御所の中立売(なかだちうり)御門」、
迎賓館の場合は「寺町側の清和院(せいわいん)御門」というように、
門の名前で行き先を告げるのが分かりやすいかと思います。
 |
 |
||
| 桂離宮 | 仙洞御所 | ||
 |
 |
||
| 京都迎賓館 | 修学院離宮 | ||
Copyright © Goto N. All Rights Reserved.